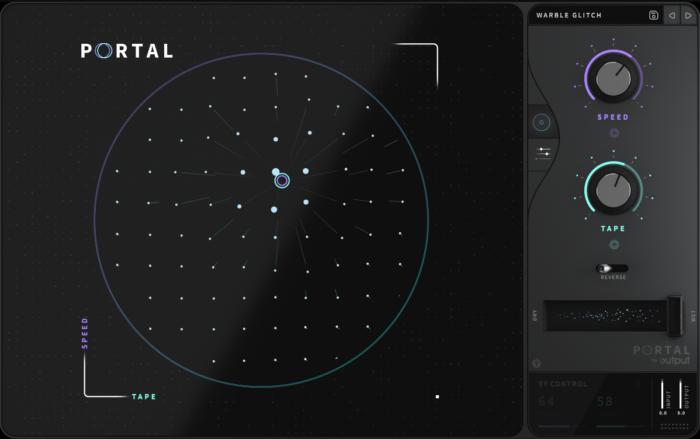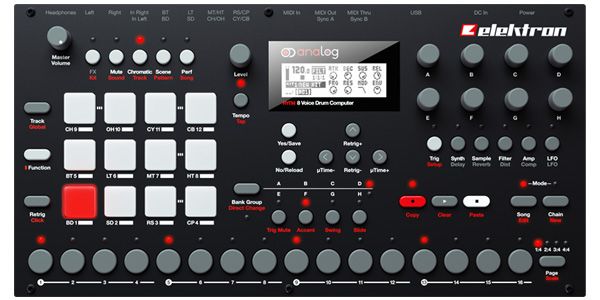Elektron Analog Rytmの使用レビューです(´◔౪◔)◞

恐らくElektronの全シリーズ中、最も操作が容易な部類で、説明書なしで行けるマシンです。
Octa trackは超絶難解ですが、Analog Rytmはボタン(パッド)を押せばすぐ音が鳴ります。
簡単(`・ω・´)
そして、なんと言っても出音がサイコー!
*過去記事を加筆修正しました
目次
12個のパッドでアナログサウンドを鳴らす極上リズムマシン
Elektron全般共通ですが、このリズムマシンも決して安くありません。


ELEKTRON ( エレクトロン ) / Analog Rytm ADS-8MK II サウンドハウス
遊びで手を出すには難しいですが、サウンドは本気( ・ὢ・ )
- パンチのあるキック
- 自然で力強い低音
- マシン独自のグルーブ感
- どこか暖かく柔らかな質感
アナログ回路が作り出す音質もさることながら、そこにElektronらしい質感が加わってます。
Elektronの作る音はパンチがあるのに柔らかいんですよね。
とても雰囲気がある音してます(´⊙౪⊙)۶
更にクラブでパフォーマンスをする場合、特に重要な体を揺らすロー感。
これがプリセット状態からしっかり出てます。
特に音作りしなくても、ローがバッチリ出てきます。
キックのチューニングが絶妙すぎ!
もちろんEQ、コンプで音に追い込むと、更に強いパンチ感を得ることも可能です。


ELEKTRON ( エレクトロン ) / Analog Rytm サウンドハウス
僕が買ったのは、初代verでしたが、現在は黒い筐体のMK2に進化しています。
Analog fourやOctatrackとの相性が抜群!
見た目が似ている三兄弟。
AFとOctaとの相性も抜群です。
elektron Octatrack MKII サンプラー
機材自体の音の作られ方が同じ方向なので、各々が混じり合くやすくグッド!

-Elektron Monomachine-
以前、monomachine(廃盤のElektronデジタルシンセ)とARを組み合わせて使ってみたのですが、この2つだと音の質感があまりにも違いすぎて、、、
お互いを馴染ませるのにかなり工夫しました。
それに比べると、Analog FourやOctaとの組み合わせは神ってます(;´༎ຶД༎ຶ`)
壮大で深い空間が簡単に作れてしまいます。
ミックスアウトのコンプどう使うか?が音作りの鍵!
Analog Rytmには
など、他の機種同様、エフェクトを各トラックにかけることができます。

そしてトラックがミックスされた最終アウトにのみ、コンプレッサーをかけられます。
バスコンプ的なコンプですね(´◔౪◔)◞
コンプレッサーは、音量のばらつきを均一にして音圧を上げたりするエフェクター。
音のまとまり感やパンチ感の調整に役立ちます。
ARのコンプはゲインリダクションメーター(コンプのかかり具合を見るメーター)も付いています。
Octaにはリダクションメーターはないので、この点とても使いやすいなと思いました。
ARのコンプを上手く使うコツは、
から設定を始めて、徐々につまみを回して調整すると上手くいきやすいです(`・ω・´)
キックのトンジェントが立つように、コンプで音を潰しすぎないのがポイント。
とはいえ、僕個人としてはあまりコンプをかけないほうが好み( ・ὢ・ )
薄ーくかけて音をまとめる使い方をしてます。
あわせて読みたい
コンプレッサーの使い方 Logic Pro編【DTM】
コンプレッサーの使い方についての記事です(`・ω・´) コンプはLogic Proだけではなく、どのDAWソフトでも必須のエフェクトです。 しかし!つまみが多いので使い方が解りづ...
あわせて読みたい
Elektron Octatrackのレビュー。ハマれば一生モノの機材になる!
Elektron製品の中でもひときわ難解と言われ、危険な匂いを放っているOctatrackについて記事です(´◔౪◔)◞ このマシン。 ほぼ新品のままオークションで売られてしまうこと...
サンプルのロードもOK
Analog Rytmはサンプラーとしても使えます!
トラックにサンプル音源を読み込めます。
ただし、サンプル自体の加工(エディット)はできません。
あらかじめ加工した音を用意する必要があります。
※mk2ではサンプリング機能が追加されているようなので、加工okになっているかもしれません。
また、アナログ発音とサンプラー音をミックスすることができます!
音の厚みを増す、キックのアタック部分を強化する、など音色調整の幅がグッと増えます(`・ω・´)
クロマチックモードで音階をつけられます
ARはクロマチックモードで音階をつけられます。
例えばカウベルの音をドレミファソラシドに変えて鳴らせます(´◔౪◔)◞
読み込んだサンプルに音階をつけることもOK。
工夫次第で、一台でも曲作りができちゃいます。
一度に鳴らせるトラックは8つですが、はっきり言って十分です(笑)
しかも、更にパラメーターロックという、神機能があります。
パラメーターロックについてはこちらの記事を参照ください。
この機能を使えば、更に自由に音色を操れます。
発音は全てモノラルです
発音した音は全てモノラルになります。
ステレオのサンプル音源を読み込んでも、モノラルに変換されます。
MK2になってもしかしたら変わってるかも、、、ここはすみません、一応お調べください。
とはいえARはリズムマシン、はっきり言ってモノラルで発音で十分です(`・ω・´)
メインはキックとスネアとハットですしね。
元々モノラルで表現するパートではあります。
Digitaktとの立ち位置の違いは?
リズムを作る、という点で似たポジションにDigitaktがあります。
二つの違いはどこか?
Digitaktはサンプラーですが、ARにもサンプル機能があります。
【即納可能】elektron Digitakt DDS-8
両者のポジションの違いは、実際使って見るまで解りづらかったですが、両方とも良いところ、微妙なところありました。
| |
Digitakt |
Analog Rytm |
| カテゴリー |
サンプラー |
リズムマシン |
| 発音回路がある |
× |
○ |
| トラック数 |
8 |
12 |
| コンプレッサー(エフェクト) |
× |
○ |
| サンプル音源読み込み |
○ |
○ |
| ソングを組む |
× |
○ |
違いをざっくり表にするとこう。
Digitaktの詳しいレビューはこちらの記事に。
音質的にはDigitaktも負けてません。
サンプル次第ですが、ちゃんと低音まで音出してくれます。
しかし、やはりDigitaktは、
- ソングが組めない
- コンプがついてない
- サンプルがないと音がならせない
など、できることは限定的。
Analog Rytmの方ができることは多いですね。
Digitaktはボイスなし、機能制限をして、サンプル加工ではOctatrackより利便性を向上、単純化させて、より直感的なトラック制作を可能にしているのが大きな特徴です。
使い方次第ではしっかり曲も作れます(`・ω・´)
Digitaktも面白いサンプラーマシンには変わりありません。
あわせて読みたい
Elektron Digitaktのレビュー。パラメーターロックが火を噴くサンプラー!
ElektronのデジタルリズムサンプラーDigitaktのレビュー記事です(´◔౪◔)◞ Digitaktは同社のOcta Trackと同じサンプラー。 機能的にはかぶる部分もあり、少し立ち位置があ...
まとめ
Elektron Analog Rytmのレビューでした!
高価なリズムマシンですが、音色は間違いなく絶品です。
チルっぽいトラックを作る時とか、特に良い感じにハマるのではないでしょうか。
最後までお読みたいだきありがとうございました!
elektron Octatrack MKII サンプラー
あわせて読みたい
Elektron Octatrackのレビュー。ハマれば一生モノの機材になる!
Elektron製品の中でもひときわ難解と言われ、危険な匂いを放っているOctatrackについて記事です(´◔౪◔)◞ このマシン。 ほぼ新品のままオークションで売られてしまうこと...
あわせて読みたい
Elektron Analog Four導入から4年目のレビュー!
Elektron Analog fourの使用レビューです(´◔౪◔)◞ -Analog FourとAnalog RytmをDAWと連携したある日- 僕はDAW中心で音楽制作をしていますが、同じくらいハード機材も好き...